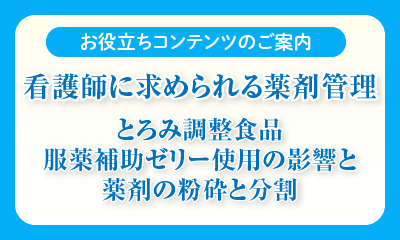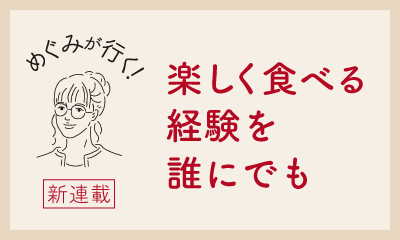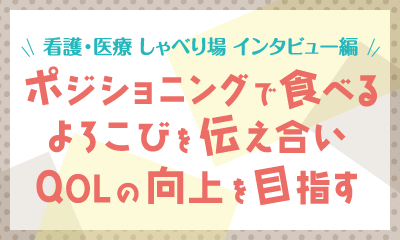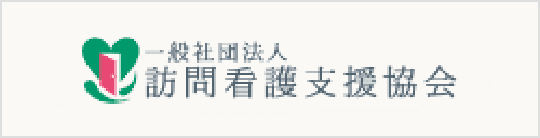菊谷 武先生の摂食・嚥下障害者ケアコラム第2回
第2回 咀嚼の話
投稿日:2011.06.22
私たち歯科医師は、咀嚼機能、嚥下機能に関する専門家として、患者に適した食形態の提案を行わなければなりません。
それには、器質的咀嚼障害の原因である、義歯の不適合や天然歯による咬合支持領域の判断も重要ですが、運動障害に対する診査も忘れてはいけません。
そこで、咀嚼運動について少し解説をします。
本来、私たちは、物を食べようとしたとき、その食べ物はどのようなものか(噛む必要のある食品なのか?舌で押しつぶして食べるものなのか?飲み込むだけで対応するものなのか?など)
を食べ物の姿を見るなどして過去の経験などから判断し、口に取り込んだのち口腔内で処理します。さらに、食べ物は口腔内に入る際に、口唇や前歯によって適当な大きさに切り取られます。
舌は食物を迎えるかのように切歯の付近まで突出されます。この時にも、口唇や舌は食べ物の物性や温度などを感知しその後の処理方法の情報を得ています。
そして、ある程度の硬さを持ち噛まなければいけない食品に対しては、舌で瞬時のうちに咀嚼側の歯の上に舌で食べ物を移動させ、舌と顎の動きの協調により上下の歯列によって粉砕処理し、唾液と混ぜられます。
もし、プリンのような柔らかい食品の場合、歯を使う咀嚼はほとんど行われず、舌と口蓋で押しつぶすように処理されます。
私たちは意識しなくても、リズミカルに下顎や舌が協調運動を行い、食塊を形成することができます。
これは、基本的な下顎のリズミカルな運動が脳幹部に存在するパターンジェネレータで、中枢性に形成されているためといわれています。
また、食べ物の硬さに対応した、噛む力のコントロールには、三叉神経を経由した歯根膜感覚と閉口筋の伸張を感知する筋感覚情報が、脳幹部での咀嚼運動の制御に重要な役割を演じているといわれています。
さらに、脳幹部ばかりでなくより高次な大脳皮質や大脳基底核も咀嚼の調整に参加していますし、味覚や歯触り、歯ごたえを感じるなど食事に必要な感覚が咀嚼の制御に影響を与えている可能性もあるといわれています。
このように、咀嚼運動の制御には、脳幹部と高次脳の両方がバランスよく協力していると考えられます。
さらに咀嚼運動の運動系においても、上位運動ニューロン、下位運動ニューロン、錐体外路系、小脳系など様々に関与しています。
これらの障害により、咀嚼に関与する筋力の低下、運動速度の異常、運動範囲の縮小、運動の巧緻性の低下、運動の安定性の不足、筋の緊張の異常などが生じ、咀嚼機能に重大な影響を与えています。
加齢とともに、さらに、さまざまな疾患や高次脳機能の低下により咀嚼運動に影響が生じます。
時に、食品の物性に応じた咀嚼運動の制御ができなくなったり、咀嚼に必要な力強い、巧みな動きができなくなったりすることがあります。これを運動障害性咀嚼障害と呼んでいます。
咀嚼にかかわる運動障害の有無や程度を判断するには摂食時の外部観察が重要です。
外部観察においては、食品の形態や物性に応じた咀嚼運動などの食品の口腔内の処理にかかわる運動の可否やその力強さ、巧みさを判断する必要があります(注)。
たとえば、噛まなければならない食品が口腔内に入っても、下顎の上下運動は見られても、食物を臼歯部に運ぶための側方運動が見られずに、舌の動きは単純な上下運動や前後運動が中心になる場合があります。
この際には、たとえ、天然歯による咬合支持が維持されていても、適合の良い義歯が装着されていても、咀嚼は困難と考えなければいけません。
一方、先にも述べましたが、咀嚼を必要としない食品が口腔内に取り込まれても、本来、咀嚼運動は必要としませんので、たとえば、ペースト食を食べている時の口の動きの観察をいくらしても、咀嚼が必要な食品を処理できる能力があるか判断することは困難です。
そこで、安全なテストフード(噛まなければ処理できないが、間違えて咽頭内に落下しないもの:サキイカなどを用い片側を口腔外に出しておく)を用いて、捕食させた後、咀嚼の運動が可能かどうか観察する必要があります。
このように、安全な食形態の決定や義歯作成の必要性にかかわる重要な要件である咀嚼機能評価は高齢者の歯科治療には欠かせない要件となります。
(注) 咀嚼運動の観察要件
●下顎の上下運動(開閉運動)
●咀嚼側に片寄る回転運動
●下顎の運動に合わせた、舌の側方運動
●咀嚼側の頬の内方への運動
それには、器質的咀嚼障害の原因である、義歯の不適合や天然歯による咬合支持領域の判断も重要ですが、運動障害に対する診査も忘れてはいけません。
そこで、咀嚼運動について少し解説をします。
本来、私たちは、物を食べようとしたとき、その食べ物はどのようなものか(噛む必要のある食品なのか?舌で押しつぶして食べるものなのか?飲み込むだけで対応するものなのか?など)
を食べ物の姿を見るなどして過去の経験などから判断し、口に取り込んだのち口腔内で処理します。さらに、食べ物は口腔内に入る際に、口唇や前歯によって適当な大きさに切り取られます。
舌は食物を迎えるかのように切歯の付近まで突出されます。この時にも、口唇や舌は食べ物の物性や温度などを感知しその後の処理方法の情報を得ています。
そして、ある程度の硬さを持ち噛まなければいけない食品に対しては、舌で瞬時のうちに咀嚼側の歯の上に舌で食べ物を移動させ、舌と顎の動きの協調により上下の歯列によって粉砕処理し、唾液と混ぜられます。
もし、プリンのような柔らかい食品の場合、歯を使う咀嚼はほとんど行われず、舌と口蓋で押しつぶすように処理されます。
私たちは意識しなくても、リズミカルに下顎や舌が協調運動を行い、食塊を形成することができます。
これは、基本的な下顎のリズミカルな運動が脳幹部に存在するパターンジェネレータで、中枢性に形成されているためといわれています。
また、食べ物の硬さに対応した、噛む力のコントロールには、三叉神経を経由した歯根膜感覚と閉口筋の伸張を感知する筋感覚情報が、脳幹部での咀嚼運動の制御に重要な役割を演じているといわれています。
さらに、脳幹部ばかりでなくより高次な大脳皮質や大脳基底核も咀嚼の調整に参加していますし、味覚や歯触り、歯ごたえを感じるなど食事に必要な感覚が咀嚼の制御に影響を与えている可能性もあるといわれています。
このように、咀嚼運動の制御には、脳幹部と高次脳の両方がバランスよく協力していると考えられます。
さらに咀嚼運動の運動系においても、上位運動ニューロン、下位運動ニューロン、錐体外路系、小脳系など様々に関与しています。
これらの障害により、咀嚼に関与する筋力の低下、運動速度の異常、運動範囲の縮小、運動の巧緻性の低下、運動の安定性の不足、筋の緊張の異常などが生じ、咀嚼機能に重大な影響を与えています。
加齢とともに、さらに、さまざまな疾患や高次脳機能の低下により咀嚼運動に影響が生じます。
時に、食品の物性に応じた咀嚼運動の制御ができなくなったり、咀嚼に必要な力強い、巧みな動きができなくなったりすることがあります。これを運動障害性咀嚼障害と呼んでいます。
咀嚼にかかわる運動障害の有無や程度を判断するには摂食時の外部観察が重要です。
外部観察においては、食品の形態や物性に応じた咀嚼運動などの食品の口腔内の処理にかかわる運動の可否やその力強さ、巧みさを判断する必要があります(注)。
たとえば、噛まなければならない食品が口腔内に入っても、下顎の上下運動は見られても、食物を臼歯部に運ぶための側方運動が見られずに、舌の動きは単純な上下運動や前後運動が中心になる場合があります。
この際には、たとえ、天然歯による咬合支持が維持されていても、適合の良い義歯が装着されていても、咀嚼は困難と考えなければいけません。
一方、先にも述べましたが、咀嚼を必要としない食品が口腔内に取り込まれても、本来、咀嚼運動は必要としませんので、たとえば、ペースト食を食べている時の口の動きの観察をいくらしても、咀嚼が必要な食品を処理できる能力があるか判断することは困難です。
そこで、安全なテストフード(噛まなければ処理できないが、間違えて咽頭内に落下しないもの:サキイカなどを用い片側を口腔外に出しておく)を用いて、捕食させた後、咀嚼の運動が可能かどうか観察する必要があります。
このように、安全な食形態の決定や義歯作成の必要性にかかわる重要な要件である咀嚼機能評価は高齢者の歯科治療には欠かせない要件となります。
(注) 咀嚼運動の観察要件
●下顎の上下運動(開閉運動)
●咀嚼側に片寄る回転運動
●下顎の運動に合わせた、舌の側方運動
●咀嚼側の頬の内方への運動
\ シェア /