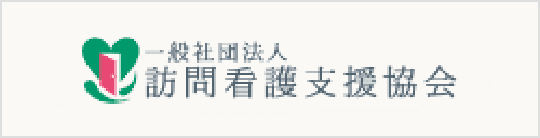災害看護の現状と課題
【第3回】被災地に暮らしを取り戻す
投稿日:2025.04.16
2024年1月1日の能登半島地震、9月の奥能登豪雨。輪島市では、災害関連死80名を含む181名が地震で尊い命を失い、豪雨では11名が犠牲に。2024年12月24日現在、234名が自宅に戻れず避難所での生活を続けています。厳しい復興への道を歩みつつ、2次避難などで能登を離れた方も戻って来られる地域にと、輪島にとどまり地域住民をささえる中村悦子先生。被災からこれまでを振り返り、これからの課題をお話いただきました。

日本財団在宅看護センター
災害時緊急支援サテライト
訪問看護ステーション リベルタ能登 エリアマネージャー
災害時緊急支援サテライト
訪問看護ステーション リベルタ能登 エリアマネージャー
中村 悦子 先生
福祉避難所で直面した課題
2024年1月1日から3月31日まで、私は社会福祉法人弘和会で訪問看護をしながら、輪島市内に設置された福祉避難所のコーデ ィネーターの補佐をしていました。医療調整本部からの依頼のあった方、障害のある方、がんの方、寝たきりの方が集中し、避難所は特養のようになっていました。
訪問ボランテ ィアナースの会「キャンナス」をはじめとする各地の看護師、「みんなの保健室」 をのれん分けしてくださったオレンジホームケアクリニック (福井市)の紅谷浩之先生および登録医の先生方が切れ目なく支援に入って下さり、医薬品、パルスオキシメーターやコロナ検査キットなどを持ち込み、災害処方箋にもすぐ対応することができました。
避難所で一番怖いのは「感染症」です。水が出ない、流せない中、マスクを用意するほか手洗いに関してはウェットテ ィッシュやアルコール消毒を徹底しました。歯磨きは泡立ちの少ない歯磨き粉を用意し、口をゆすいだら吸水パッドを敷いたガーグルベースンに吐き出して、パッドをゴミとして捨てるようにしていました。
週末には「ふるふる隊」という被災地での口腔ケアや摂食嚥下支援をサポートする口腔ケアチームが来てくださったので、この避難所では誤嚥性肺炎を発症した患者さんはいませんでした。治療が必要な場合は、地域の歯科医師会経由でかかりつけの歯医者さんにつなぐ流れも作り、地元の仕事の妨げにならない配慮もなされました。
当時、勤務していた輪島市内の訪問看護ステーションの利用者さんは60人ほどで、安否確認は被災後すぐに行いましたが、いずれかの形で最終的に全員の確認が取れたのは、2月に入ってからです。1月末でも病院は停電・断水が続き、避難所も水が出ないので、1.5次避難・2次避難された方が多く、地元に残った方は5人、職員も退職したり、避難先から戻れずに4人に減りました。
一般の避難所に患者さんを訪ねたときは、栄養状態を観察しながら「とろみがないとお茶が飲めない」「吸収力の悪いオムツしかない」「便秘に効くものがほしい」などの要望を伺い、必要な方にお渡ししました。体育館のような避難所には、水分やカイロはありますが、細かい生活物資は行き届いてなかったのです。
食品はバラバラに、しかも保存がきくパン、カップ麺、菓子類と、炭水化物ばかり大量に届くのです。「何が欲しい?」と聞かれたら、新鮮な果物(バナナ、みかんなど)や、たんぱく質を多く含む魚肉ソーセージやチーズ入りかまぼこなどをお願いしていました。後から聞いた話では、野菜が摂れないからと飲んでいた野菜ジュースの種類によっては、心不全や高カリウム血症を発症し、避難所から搬送された人もいたそうです。

避難してきた人たちの困りごとに耳を傾け、栄養状態もチェック(2024.1.1~3)
「リベルタ能登」を拠点に戻れる環境を整える
災害発生時には、物事の緊急度と重症度を見極め、優先順位をつけて行動することが求められます。しかし、日常的な業務の中では判断できる事柄でも、災害時には複雑な状況が起こり、判断を迷うことも出てきます。
震災後、笹川保健財団の喜多悦子会長から「欲しいものはないか」とご連絡いただき、私は「シェルターが欲しい」とお答えしました。多くの家屋が潰れ、停電・断水が続き、介護職員も避難してほとんどいないという状況。寝泊りできるところがあれば専門職が帰ってくるのではないかと考えたのです。石川県には日本財団在宅看護センター 「リベルタ金沢」があり、喜多会長から「金沢に緊急支援のシェルターを一 つ、輪島に災害時緊急支援サテライトという形で訪問看護ステーションを作りますか」とご提案いただきました。

そこで私は弘和会を退職し、 4月1日に災害時緊急支援サテライト訪問看護ステーション「リベルタ能登」 (輪島市) を立ち上げました。 あまり被災してない一軒家をお借りして、 1階は事務所、 2階は住まいとしました。 ここを拠点に、 金沢や県外に避難された患者さんや職員が輪島に戻ってくることのできる環境を整えていきたいと思っています。
災害時は要配慮者に留意しますが、救援物資などの配布をはじめ、その時点で誰が優先されるべきなのかは複雑な状況によって変わってきます。普段から話し合って考えておくことも大事ですし、その場で話し合って決めたことに関しては 「あの時ああすればよかった」などと後で言わないことも大切です。みんなで決めたことが最良であり、普段から意見を出し合える風土づくりが大切だと言えます。
日常を大事にし地域力を高める
2007年の能登半島地震での被災経験も合わせて考えるのは、日頃の備えの大切さです。日頃から自分の体をしっかり守り医療に依存しないためには、「食べる・出す・動く・喋る・集まる」が大事です。食べていないと出ない。すっきり出ないと気持ち悪い。食べていれば動けて、出かけて、知り合いや友達とお茶を飲みながら話ができます。また、部屋が散らかっていると、避難するときに持ち出す大切なものがどこにあるのかわかりません。住民一人ひとりの日頃からの心がけが大切です。
現在、二重被害や泥出しで心折れている人が多くいます。1人ではないことを体で感じてもらうためには、コミュニテ ィの形成が一番の課題です。朝市の人たちも、海で頑張っている人たちも一 つになって、みんなでどうしたいかを考えて、地域力をつけていきたい。
喜多先生の 「看護師が日本を変える」に共感している一人として、医療の視点だけではない新しい街づくりで、地域の人々の生活を守ることを考えています。チーム医療では薬剤師・管理栄養士・リハビリのスタッフと繋がる。在宅医療では、歯科医・歯科衛生士・介護従事者、みんなと繋がりを持って、「あのことはあの人に聞けばわかる」と正しい情報を共有して一緒に進んでいく。そうすることで訪問看護の目標である「安心して生活できる地域作り」が出来るのだと思います 。
訪問看護の目標
医療の前をささえる
・疾病を予防し医療に依存しない身体づくり
・入院しても合併症を回避して早々に退院できる基礎体力の維持
・入院しても合併症を回避して早々に退院できる基礎体力の維持
医療の後をささえる
・退院後も障害が残ったり継続的なケアや処置が必要であっても安心して生活できる地域作り
能登に生まれたことを、能登で生きていくことを後悔させない看護を提供
その 一方、「住み慣れた地域であなたらしく」 を掲げてはいるものの、被災すれば「住み慣れた地域」を離れどこで生きていくかわからないという現実もあります。支援に頼るだけでなく、どこへ行っても生き抜く力を育てるのも、私たちの仕事であることを痛感しています。
病院ナースの皆さんには、日頃から患者さんの生活を見てほしいと思います。その人がどこから来て、どこへ帰るのか。何かあったときに、生きていける力があるのか、助けてくれる人がいるのか、そういう視点を持つと、在宅生活につなぐアドバイスにも活かせるでしょう。個々の生活を見据えた看護を実践していくことが、災害をはじめとする様々な壁を乗り越えて生き抜く力のささえになるのではないでしょうか。
写真提供 中村悦子先生
\ シェア /