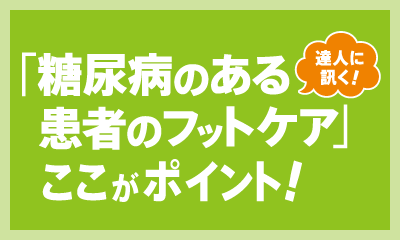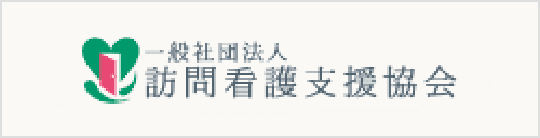ナースマガジンvol.50
達人に訊く!「患者から学ぶ『食べること』-看護を変える気づき-」ここがポイント!
投稿日:2025.02.19
胃ろう造設や経口摂取の選択は、患者さんや家族にとって簡単に答えの出るものではありません。看護師には、患者さんの気持ちに寄り添い、悩みや迷いに一緒に向き合いながら、その人らしい最善の道を探す力が求められます。リスクを見極め、何度も試行錯誤を繰り返しながら支えるケアの現場について、今回は高崎総合医療センターの板垣七奈子先生に、実際の症例をもとにお話を伺いました。
患者から学ぶ「食べること」 ―看護を変える気づき―の達人

板垣 七奈子 先生
高崎総合医療センター
NST栄養サポート室長
摂食嚥下障害看護認定看護師
NST栄養サポート室長
摂食嚥下障害看護認定看護師
今回の症例にはあげませんでしたが、人生の最終段階、いわゆる終末期になると、誤嚥のリスクを避け、安全性のみを優先して食べることを諦めてしまうことも多いです。
しかし、美味しい食事を楽しく食べることは、人生の大きな楽しみ、生き甲斐であり、個人の価値観などを考慮しACPを行いながら、患者さんやご家族の意思を十分に確認したうえで積極的に経口摂取を支援していきましょう。
しかし、美味しい食事を楽しく食べることは、人生の大きな楽しみ、生き甲斐であり、個人の価値観などを考慮しACPを行いながら、患者さんやご家族の意思を十分に確認したうえで積極的に経口摂取を支援していきましょう。
迷いながらも共に最善の選択を探る
胃ろう造設や経口摂取の選択に求められる看護師のチカラ
胃ろう造設や経口摂取において、患者さんの選択を支えるための関わりが重要です。その選択が、患者さんの未来にどのような可能性をもたらすのかを、左右してしまうこともあるからです。胃ろうを造設することで患者さんの体力を維持し、経口摂取への道をつなぐ手段となることもありますが、一方で、経口摂取を維持すれば不要な胃ろうの造設を避けられるケースもあります。
看護師は、患者さんにとっての最善の選択を一緒に見つけ、支えることができる存在であり、それだけのチカラがあります。私自身、これまで多くの患者さんと出会い、その価値観や人生観の多様さに何度も驚かされました。患者さん一人ひとりが持つ「どう生きたいのか」という思いに寄り添い、その声に応えることが看護師の大きな役割だと感じています。
リスクを知り、攻めと守りで可能性を探る
患者さんの選択の場面で私が大切にしているのは、恩師から教わった「リスクを知って可能性を探る」という言葉です。患者さんの状態を丁寧に評価し、リスクを見極めた上で適切なアプローチを行えば、その人の中に眠る力を引き出すことができます。リハビリやケアは、守りの姿勢だけでは不十分です。時には積極的に『攻め』の姿勢を持ち、『この疾患だからできない』と決めつけるのではなく『何ができるのか』を徹底的に考える。これが看護師の腕の見せ所だと思います。
看護師には、患者さんの可能性を引き出し、その方の人生が豊かになる選択を支える関わりが求められます。ここからは、価値観を知ることの大切さ、選択を支えるケアの重要性について、私が経験した症例をもとにご紹介します。
看護師の役割
■患者の価値観や思いに寄り添う姿勢を 持つこと
■リスクを見極め、「何ができるか」を考え可能性を探ること
■守りと攻めのバランスで患者の力を引き出すこと
■人生を豊かにする最善の選択を共に考えること
■リスクを見極め、「何ができるか」を考え可能性を探ること
■守りと攻めのバランスで患者の力を引き出すこと
■人生を豊かにする最善の選択を共に考えること
症例紹介
症例1
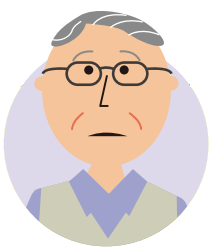
F氏
70歳 男性
食事中の窒息により気管切開を行い、入院にて治療・リハビリ中。
既往:脳梗塞(後遺症なし)
70歳 男性
食事中の窒息により気管切開を行い、入院にて治療・リハビリ中。
既往:脳梗塞(後遺症なし)
自宅で食事中、寿司を誤嚥し窒息。
救急搬送され、気管切開し入院となった。
経口摂取の再開を目指してリハビリに励んでいるが、痰の分泌が多く、肺炎を繰り返し発症していた。
救急搬送され、気管切開し入院となった。
経口摂取の再開を目指してリハビリに励んでいるが、痰の分泌が多く、肺炎を繰り返し発症していた。
「食べる 」よりも「話す 」ことを選択
F氏は嚥下機能の低下があり、このままリハビリを続けても経口摂取は難しい状況でした。肺炎を繰り返していたこともあり、医師より喉頭気管分離術が提案されました。食べることを優先して気管を分離するか、声を残すために食べることを諦めるか、という選択に、F氏は気管分離をしないと言いました。私はてっきり食べることを優先するだろうと思っていたので、この選択は驚きでした。
価値観を踏まえた意思決定が重要
理由を聞いてみると、家族やお孫さんと話したいという思いがあったことがわかりました。F氏は普段から、言いたいことはこまめにメモに書き、筆談で会話をしていました。しかし、まだ幼いお孫さんと筆談は難しいため「声で話したい」と希望されたのです。「食べる」ことを選択し、気管分離をしない方針となりました。F氏が決断するまでは、医師も私も「ご飯を食べられるなら声が出なくなってもいいだろうと思っていましたが、それは私たちの押し付けでした。食べることだけがすべてではなく、その方の価値観を踏まえた意思決定支援が大切だと学べる経験でした。
症例2

B氏
80歳 女性
誤嚥性肺炎を発症し、治療目的で入院中。
既往:軽度の認知症
80歳 女性
誤嚥性肺炎を発症し、治療目的で入院中。
既往:軽度の認知症
介護施設に入所中、誤嚥性肺炎にて入院となった。認知機能の低下はあるが、意思疎通は良好。経鼻胃管は自己抜去してしまうため、高カロリー輸液にて栄養を投与していた。誤嚥性肺炎は改善し、経口摂取に向けたリハビリが始まった。
食事を認識できないことが経口摂取を妨げていた
茶碗に盛った白米も同様で、白い茶碗と白米の白色が重なり、白米が入っていることを認識できていなかったようです。そこで、茶碗を黒色にしたところ、白米を認識してペロッと完食できました。
認知機能低下により食事を認識できないことがあるとは知っていましたが、B氏の認知症はごく軽度であり、認知機能も保たれていたため、気づくのに時間がかかっていました。しかし、B氏のように、食べられない理由をうまく表出できない方もいます。認知症のある方への胃ろう造設が社会問題になっていますが、B氏も、原因に気づかなければ胃ろうを増設していたかもしれません。
私たちは、機能的な評価だけでなく、食事についてあらゆる角度から評価しなければならないという学びになりました。全身をアセスメントし、リスクを知った上で「食べる」という選択肢を支えていかなければならないと思います。
\ シェア /