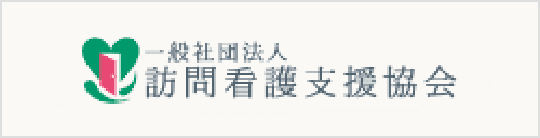編集部レポート
「どうすればよかったか?」家族と医療のはざまで――姉の統合失調症と向き合ったドキュメンタリー映画が問いかけるもの
投稿日:2024.11.29
20年以上にわたり家族の姿を記録し続けた映画『どうすればよかったか?』は、統合失調症のある姉と家族の葛藤を描いたドキュメンタリーです。

優秀で面倒見の良かった姉が、ある日突然、現実とは思えない言葉を叫び始める―。
統合失調症が疑われても、医師である両親はその診断を否定。弟である藤野知明監督は無力感を抱えながらも「事実を残すため」にカメラを回し続けました。
そこに映されたのは、届かない助けと家族の分断、そして答えのない問い。「どうすればよかったのか」という言葉に込められた監督の想いと、家族との分かりあえなさ、そして医療や社会へのメッセージについて、編集部でお話を伺いました。
統合失調症が疑われても、医師である両親はその診断を否定。弟である藤野知明監督は無力感を抱えながらも「事実を残すため」にカメラを回し続けました。
そこに映されたのは、届かない助けと家族の分断、そして答えのない問い。「どうすればよかったのか」という言葉に込められた監督の想いと、家族との分かりあえなさ、そして医療や社会へのメッセージについて、編集部でお話を伺いました。
事実を残すためにカメラを回し始めた
編集部:
私は看護師という立場ではありますが、映画を拝見して、統合失調症の方の実際の様子をきちんと見たのは初めての経験でした。
私は看護師という立場ではありますが、映画を拝見して、統合失調症の方の実際の様子をきちんと見たのは初めての経験でした。
藤野監督:
「病院と繋がってない患者」を目にする機会はなかなかないですよね。メディアでは、比較的安定した状況になってから撮影が始まることがほとんどだと思うので、混沌とした状態で撮れたのは自分自身が家族だったからだと思います。
「病院と繋がってない患者」を目にする機会はなかなかないですよね。メディアでは、比較的安定した状況になってから撮影が始まることがほとんどだと思うので、混沌とした状態で撮れたのは自分自身が家族だったからだと思います。
編集部:
初めてカメラを回そうと思ったのは、どのようなお気持ちからだったんですか?
初めてカメラを回そうと思ったのは、どのようなお気持ちからだったんですか?
藤野監督:
最初はドキュメンタリーを撮ろうという考えはありませんでした。
1992年、姉が頻繁に興奮状態を起こすようになって、ウォークマンで録音したのが始まりです。
「記録を残そう。そうしないと、事実がどんどん消えて行ってしまう―。」
そう思って、初めて録音したのが映画の冒頭に使われた音声です。
当時、姉とはもう何年も姉弟としての会話が出来ていない状態でした。だから、映像を撮りながらいつかまた姉と会話が出来るようになったら嬉しいな、というような気持ちもあったのかもしれません。
最初はドキュメンタリーを撮ろうという考えはありませんでした。
1992年、姉が頻繁に興奮状態を起こすようになって、ウォークマンで録音したのが始まりです。
「記録を残そう。そうしないと、事実がどんどん消えて行ってしまう―。」
そう思って、初めて録音したのが映画の冒頭に使われた音声です。
当時、姉とはもう何年も姉弟としての会話が出来ていない状態でした。だから、映像を撮りながらいつかまた姉と会話が出来るようになったら嬉しいな、というような気持ちもあったのかもしれません。
編集部:
冒頭の音声はとても衝撃的で、視聴者の心に強く印象を残すシーンだったと思います。
お姉さんの病状が現れた当時は、どのようなご様子だったのでしょうか?
冒頭の音声はとても衝撃的で、視聴者の心に強く印象を残すシーンだったと思います。
お姉さんの病状が現れた当時は、どのようなご様子だったのでしょうか?
藤野監督:
1983年、僕が高校2年生、姉が24歳で大学の3年生くらいのときでした。
当時の僕と姉は、晩ごはんを食べてすぐ寝て、夜中の1時に起きて朝まで勉強するという、ちょっと変則的な生活をしていたんです。その頃から姉はヒステリックになることもあったんですが、それでも説明がつく範囲でした。
しかしある日、急に30分くらい大声で叫びだしたんです。
瞳孔が開いて、現実とはかけ離れた内容を言い続けていました。これはどうにもできないと思い、救急車を呼んで病院に行きました。ところが翌日、「精神科にいることはかえって心の傷になると説明された」と父が言って退院してきたんです。
そこから激しい症状が繰り返されるようになりました。
1983年、僕が高校2年生、姉が24歳で大学の3年生くらいのときでした。
当時の僕と姉は、晩ごはんを食べてすぐ寝て、夜中の1時に起きて朝まで勉強するという、ちょっと変則的な生活をしていたんです。その頃から姉はヒステリックになることもあったんですが、それでも説明がつく範囲でした。
しかしある日、急に30分くらい大声で叫びだしたんです。
瞳孔が開いて、現実とはかけ離れた内容を言い続けていました。これはどうにもできないと思い、救急車を呼んで病院に行きました。ところが翌日、「精神科にいることはかえって心の傷になると説明された」と父が言って退院してきたんです。
そこから激しい症状が繰り返されるようになりました。
編集部:
その後、お姉さんの生活はどのようなご様子だったのでしょうか?
その後、お姉さんの生活はどのようなご様子だったのでしょうか?
藤野監督:
風呂に入らず頭もベタベタの状態で、真夜中にクリームシチューのルーをそのまま食べるような、そんな生活を送っていました。
そして2005年、母が玄関のドアに南京錠をつけ始めたんです。そのとき、「これはもうやばい、なんとかしなければ」と思いました。
風呂に入らず頭もベタベタの状態で、真夜中にクリームシチューのルーをそのまま食べるような、そんな生活を送っていました。
そして2005年、母が玄関のドアに南京錠をつけ始めたんです。そのとき、「これはもうやばい、なんとかしなければ」と思いました。

それからは頻繁に実家に帰るようにして、鍵を外すように言いました。
出入りが自由になったのはよかったんですけど、その代わり夜中に出て行っちゃうから、警察官が突然家に来ることもありました。
人に迷惑をかけることになるけれど、それでも鍵をつけるべきじゃないと僕は思っていました。
出入りが自由になったのはよかったんですけど、その代わり夜中に出て行っちゃうから、警察官が突然家に来ることもありました。
人に迷惑をかけることになるけれど、それでも鍵をつけるべきじゃないと僕は思っていました。
相談まで9年、再診まで25年 その背景にある見えない壁
編集部:
当時監督が感じていた困難には、どのようなものがありましたか?
当時監督が感じていた困難には、どのようなものがありましたか?
藤野監督:
一番大変だったのは、相談できる人がいなかったことでした。
学校の友人にはなかなか言えませんでした。統合失調症かどうかも定かでないときに、変な噂が広まるのではないかと思って言えなかったんです。
私の成績を心配してきた教員に家族の事情を打ち明けたこともあったのですが、「姉さんが精神障がいなら、お前もか?」と言われてしまい、それ以来、他人に相談するのをためらうようになりました。
それでも、25歳のとき学生相談室に行ってプロの方に聞もらえたことで、だいぶ前に進めました。姉が発症したのが僕が16歳のときだったので、ちゃんと相談できるまで9年かかりました。
一番大変だったのは、相談できる人がいなかったことでした。
学校の友人にはなかなか言えませんでした。統合失調症かどうかも定かでないときに、変な噂が広まるのではないかと思って言えなかったんです。
私の成績を心配してきた教員に家族の事情を打ち明けたこともあったのですが、「姉さんが精神障がいなら、お前もか?」と言われてしまい、それ以来、他人に相談するのをためらうようになりました。
それでも、25歳のとき学生相談室に行ってプロの方に聞もらえたことで、だいぶ前に進めました。姉が発症したのが僕が16歳のときだったので、ちゃんと相談できるまで9年かかりました。
編集部:
専門職に聞いたほうがいい場面と、そうではない場面があると思いますが、監督ご自身の経験からどなたに相談するのがよかったと思いますか?
専門職に聞いたほうがいい場面と、そうではない場面があると思いますが、監督ご自身の経験からどなたに相談するのがよかったと思いますか?
藤野監督:
経験則になりますが、僕の場合は飲み屋のおじちゃんやおばちゃんがよく話を聞いてくれました。
「うんうん」とただ話を聞いてくれることに救われました。
爆発寸前の頭の状態だったから、ただ話を聞いてくれるだけでその圧が下がるんです。
もちろん、前に進むためには専門的なアドバイスというのが必要だと思いますが、まずは「ただ聞いてくれる人」がいるだけで、どれだけ助かるかが身に染みてわかりました。
経験則になりますが、僕の場合は飲み屋のおじちゃんやおばちゃんがよく話を聞いてくれました。
「うんうん」とただ話を聞いてくれることに救われました。
爆発寸前の頭の状態だったから、ただ話を聞いてくれるだけでその圧が下がるんです。
もちろん、前に進むためには専門的なアドバイスというのが必要だと思いますが、まずは「ただ聞いてくれる人」がいるだけで、どれだけ助かるかが身に染みてわかりました。
編集部:
丸ごと受け止めてもらえるだけでもよかったんですね。
読者の方はいろんな立場のご家族に出会う場面があると思うので、その方たちに向けて伝えられたらいいなと思います。
相談するまでに9年かかり、さらに再診までは25年かかったと伺っていますが、受診に至るまでどのようなハードルがありましたか?
丸ごと受け止めてもらえるだけでもよかったんですね。
読者の方はいろんな立場のご家族に出会う場面があると思うので、その方たちに向けて伝えられたらいいなと思います。
相談するまでに9年かかり、さらに再診までは25年かかったと伺っていますが、受診に至るまでどのようなハードルがありましたか?

藤野監督:
無理やり病院に連れて行けばいいんだと言う人がいましたが、それは現実的ではありませんでした。車に乗せても大人しく乗っていてくれないし、暴れて降りてしまう。さらにうちの場合は、連れていけても両親が退院させてしまうんですよ。
結局、父か母のどちらかが倒れるまで待つしかありませんでした。
母が認知症になったことで、父はギブアップしました。
二人で一人は診られるけど、一人で二人は診られない。
そういうわけで25年経ってしまいました。
これだけ情報が取りやすい時代でも、医療にたどりつけない現実があるんです。
家族がいいほうに働くこともあれば、悪いほうに働くこともある。
今では当事者が情報発信をしていたり、仕事を持っていたりしますが、技術とは別の、見えない壁みたいなものは依然として立ちはだかっていると感じます。
無理やり病院に連れて行けばいいんだと言う人がいましたが、それは現実的ではありませんでした。車に乗せても大人しく乗っていてくれないし、暴れて降りてしまう。さらにうちの場合は、連れていけても両親が退院させてしまうんですよ。
結局、父か母のどちらかが倒れるまで待つしかありませんでした。
母が認知症になったことで、父はギブアップしました。
二人で一人は診られるけど、一人で二人は診られない。
そういうわけで25年経ってしまいました。
これだけ情報が取りやすい時代でも、医療にたどりつけない現実があるんです。
家族がいいほうに働くこともあれば、悪いほうに働くこともある。
今では当事者が情報発信をしていたり、仕事を持っていたりしますが、技術とは別の、見えない壁みたいなものは依然として立ちはだかっていると感じます。
姉は社会との繋がりを求めているのがわかった
編集部:
お姉さんの退院後、表情がとても穏やかだと感じて、私も思わず頬が緩みました。監督ご自身は当時どう感じていましたか?
お姉さんの退院後、表情がとても穏やかだと感じて、私も思わず頬が緩みました。監督ご自身は当時どう感じていましたか?
藤野監督:
統合失調症の症状はあっても、本人の個性というのは残ります。
退院して、「個性の部分がどのくらい戻るのかなあ、ここはよくなったんだ。じゃあもっとよくなるかな?」という感じで姉を見ていました。
人間は社会的な生き物だし、集団の中で自分自身の存在を感じるものだと思うんです。
姉はそれを感じるために物をたくさん買っていました。
「ありがとうございました」と言われることに社会との関係性を感じていたんだと思います。
僕はその様子を見て、「姉にはコミュニケーションをとりたい気持ちがあるんだ。
じゃあ作業所に行って、違う価値観の人と一緒にいて関わっていけばもっとよくなるんじゃないか?」と考えていたのですが、姉は行きたがりませんでした。あそこに行くなら自殺する、と。
統合失調症の症状はあっても、本人の個性というのは残ります。
退院して、「個性の部分がどのくらい戻るのかなあ、ここはよくなったんだ。じゃあもっとよくなるかな?」という感じで姉を見ていました。
人間は社会的な生き物だし、集団の中で自分自身の存在を感じるものだと思うんです。
姉はそれを感じるために物をたくさん買っていました。
「ありがとうございました」と言われることに社会との関係性を感じていたんだと思います。
僕はその様子を見て、「姉にはコミュニケーションをとりたい気持ちがあるんだ。
じゃあ作業所に行って、違う価値観の人と一緒にいて関わっていけばもっとよくなるんじゃないか?」と考えていたのですが、姉は行きたがりませんでした。あそこに行くなら自殺する、と。
そうしている間に、姉にがんが見つかりました。
痰が絡む咳をしていて、部屋がきれいじゃないから結核かな、と思ったんですけど、実際にはステージ4のがんでした。
痰が絡む咳をしていて、部屋がきれいじゃないから結核かな、と思ったんですけど、実際にはステージ4のがんでした。

仕組みが整わない限り
受け皿は家族だけになり、孤立していく
編集部:
当事者からして、あったらよかったと思う制度はありますか?
例えば、本人が病院に行けないのに診断書を求められることはハードルが高いと思うのですが、家族だけで受診ができたり、先生が訪問診療してくれる仕組みがあれば良かったのではないでしょうか?
当事者からして、あったらよかったと思う制度はありますか?
例えば、本人が病院に行けないのに診断書を求められることはハードルが高いと思うのですが、家族だけで受診ができたり、先生が訪問診療してくれる仕組みがあれば良かったのではないでしょうか?
藤野監督:
そんな発想があったら、本当に助かったと思います。でも、当時はそういうことを考える余裕もありませんでした。
精神科受診を終着駅だと考えている人はまだまだ多いんです。
本来は出発点や通過点であって、そこから先に未来が開けているはずなのに。
そう感じられる世の中に変わっていく必要があるのかな、と思います。
そんな発想があったら、本当に助かったと思います。でも、当時はそういうことを考える余裕もありませんでした。
精神科受診を終着駅だと考えている人はまだまだ多いんです。
本来は出発点や通過点であって、そこから先に未来が開けているはずなのに。
そう感じられる世の中に変わっていく必要があるのかな、と思います。
編集部:
偏見や誤解がまだあるということですよね。
偏見や誤解がまだあるということですよね。
藤野監督:
はい。理解は少しずつ広まっていると感じることもありますが、一方で、精神障がい者が事件を起こしたと報道されれば「閉じ込めておけ」という書き込みが溢れます。
私は、精神障がいを患っても本人や家族が恥じたり隠したりする必要がなく、障がいのある人が社会の中で安心して暮らせる社会になることを望んでいます。
この映画を通して、私たち家族がどのように統合失調症に対応したかを見せることは、統合失調症についての理解を深めてもらう機会になると考えています。
はい。理解は少しずつ広まっていると感じることもありますが、一方で、精神障がい者が事件を起こしたと報道されれば「閉じ込めておけ」という書き込みが溢れます。
私は、精神障がいを患っても本人や家族が恥じたり隠したりする必要がなく、障がいのある人が社会の中で安心して暮らせる社会になることを望んでいます。
この映画を通して、私たち家族がどのように統合失調症に対応したかを見せることは、統合失調症についての理解を深めてもらう機会になると考えています。

2024年12月7日(土)より東京を皮切りに全国順次公開予定。
詳しい公開スケジュールはWEBサイトよりご確認ください。
詳しい公開スケジュールはWEBサイトよりご確認ください。
監督・撮影・編集:藤野知明
制作・撮影・編集:淺野由美子
編集協力:秦岳志
整音:川上拓也
製作:動画工房ぞうしま
配給:東風
2024年/101分/日本/DCP/ドキュメンタリー
(C)2024 動画工房ぞうしま
制作・撮影・編集:淺野由美子
編集協力:秦岳志
整音:川上拓也
製作:動画工房ぞうしま
配給:東風
2024年/101分/日本/DCP/ドキュメンタリー
(C)2024 動画工房ぞうしま
編集後記
現代社会が「ストレス社会」と呼ばれるようになって久しい中、わが国では少子高齢化、長引く不況、核家族化による家族機能の低下、地域との連帯や相互扶助の喪失といった複雑な背景が重なり、さまざまな精神科的な問題が生じています。
こうした状況の中で、精神科医による診断や治療といった「医療」は不可欠な存在です。しかし、精神疾患は長期的な支援を必要とする場合が多く、医療だけで完結するものではありません。そのため、診断や治療を支える「保健」の取り組みや、患者さんが地域の中で生活を続けられるようにする「福祉」の役割も同じくらい重要だと感じます。
その中で重要になるのが、精神疾患を防ぐ「保健」の取り組みや、慢性患者の介護と地域社会への復帰を支える「福祉」の役割ではないでしょうか。
特に統合失調症は、100人に1人が罹患すると言われるほど身近でありながら、患者さんやその家族が孤立し、適切なサポートを受けられないケースも少なくありません。病気について気軽に話せる環境や、助けを求められる社会を実現するには、医療、保健、福祉が連携して支援を続ける仕組みが求められます。この現実を前に、誰もが病気のことを自然に話し、助けを求められる社会の実現が求められています。
看護師として、地域住民として、そして一人の親として、私たちに何ができるのか。この問いを常に自分に投げかけることが必要です。この映画を通じて感じたその思いを、読者の皆様と共有したいと思います。これをきっかけに、少しでも「誰もが安心して支え合える社会」について考える一助となれば幸いです。
こうした状況の中で、精神科医による診断や治療といった「医療」は不可欠な存在です。しかし、精神疾患は長期的な支援を必要とする場合が多く、医療だけで完結するものではありません。そのため、診断や治療を支える「保健」の取り組みや、患者さんが地域の中で生活を続けられるようにする「福祉」の役割も同じくらい重要だと感じます。
その中で重要になるのが、精神疾患を防ぐ「保健」の取り組みや、慢性患者の介護と地域社会への復帰を支える「福祉」の役割ではないでしょうか。
特に統合失調症は、100人に1人が罹患すると言われるほど身近でありながら、患者さんやその家族が孤立し、適切なサポートを受けられないケースも少なくありません。病気について気軽に話せる環境や、助けを求められる社会を実現するには、医療、保健、福祉が連携して支援を続ける仕組みが求められます。この現実を前に、誰もが病気のことを自然に話し、助けを求められる社会の実現が求められています。
看護師として、地域住民として、そして一人の親として、私たちに何ができるのか。この問いを常に自分に投げかけることが必要です。この映画を通じて感じたその思いを、読者の皆様と共有したいと思います。これをきっかけに、少しでも「誰もが安心して支え合える社会」について考える一助となれば幸いです。
\ シェア /